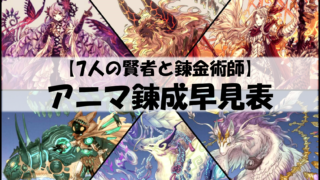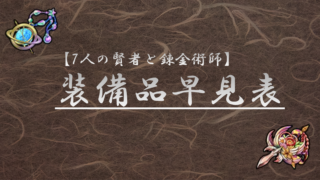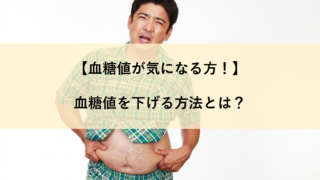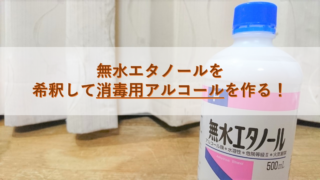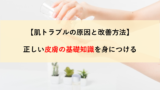ニキビ等の肌トラブルに悩まされている方は多いと思います。
色々な化粧品を使っているにも関わらず肌トラブルが改善しない方もいると思います。
それは、ニキビや肌トラブルの原因が正確にわかっていないからかもしれませんよ?
ニキビや面疔(ニキビと似て非なるもの)ができるのは細菌が関係しています。
多くの方にできるニキビの直接的な原因はアクネ菌という細菌の増殖ですが、アクネ菌が増える根本的な要因が存在します。
面疔の原因は黄色ブドウ球菌という菌によるものです。
今回は肌トラブルの原因になる細菌の種類と役割知って頂ければと思います。
細菌とニキビとの関係もこの記事内で軽くお伝えしていきます。
皮膚に生息する細菌の種類と役割
ヒトは微生物と共存することで様々な恩恵を受けています。意外と大事なんです。
代表的なものには腸内細菌ですね。悪玉菌やビフィズス菌などの善玉菌は有名ですよね。
この常在細菌はヒトに様々な影響を与えます。
同じように、細菌は全身の皮膚にもいっぱい存在し、常在細菌叢を形成しています。
つまり、顔などの皮膚にも細菌はいて様々な役割を担っています。
実はこの細菌達はスキンケア(肌の健康)を維持する上でとても重要な働きをしてくれているんですね。これを知っていたらなんでスキンケアの方法を見直そうかと考えるか知れません。
それでは少しずつ詳しく見ていきましょう。
常在細菌叢の常在(定常)菌と一過性細菌叢の通過菌
まずは細菌が住んでいる場所を理解しましょう。省略したい場合は小まとめまで飛ばして構いません。
細菌の住処
皮膚の細菌の住について良くわかる実習があります。
微生物の実習で必ずといってもよいほど行われる「パームチェック」を用いた手指衛生の実習です(私もしました)。
それは
- ①石鹸洗いのみ
- ②石鹸洗い後にアルコール消毒する
①または②を行い、手形の形をした培地に手を軽く押し当てて菌が増殖するかどうかを確認するテストです(培地=細菌を育てる餌が入った家です)。
石鹸洗いした結果は下記の写真のようになります。

石鹸洗いした場合 、「(1)の洗浄前」で手に何も施さなければ、培地で菌は増えます。 「石鹸で洗浄後」は洗浄前よりも細菌の発育は少なくはなることがわかりましたね。
では「石鹸洗い後にアルコール消毒する」では最近の発育にどのような違いがみられるでしょうか。

結果は石鹸洗い後にエタノール消毒をしたほうが石鹸のみと比べて細菌の増殖が抑えられるという結果になります。
石鹸→アルコール消毒の順番で消毒することが感染防御に効果的だということがわかりますね。
この研究に用いた消毒薬は、グルコン酸クロルヘキシジンといいエタノール(エチルアルコール)消毒と同じように手指消毒に用いることができる消毒薬です。エタノールでも同様の効果はあります。
エタノールやこのグルコン酸クロルヘキシジンはコロナウイルスやインフルエンザ等のエンベロープのあるウイルスや一般細菌に対して効果がありますので是非感染が流行している時は積極的に使っていきましょう。
また、グルコン酸クロルヘキシジンはエタノールに被れやすい方にも使うことができます。
ここでもう一度、表皮の構造を見てみましょう。

石鹸は界面活性剤ですから、油分を洗い流せることは周知のことだと思います。
皮脂層は角質層の上にあり、殆ど油分であることは前回の記事でお伝えしましたので、石鹸は皮脂層の皮脂を落としてくれます。
石鹸のみでは細菌の数が少なくなったのは、そこに住み着いている細菌がいて、 皮脂と一緒に石鹸で落ちる菌がいることを表しています。
さらに石鹸後にアルコール消毒をして菌の発育がほとんどなくなったということは、皮脂層の下の角質層からも菌がいなくなったということを表しているのです。
実は、皮脂層で流れてしまう細菌を「通過細菌または一過性細菌」と言い、アルコール消毒で消えてしまった細菌を「定常菌または常在菌」と呼ばれていて角質層の上層に常にいるのです。また、それら菌が生息し形成する環境を「~叢(そう)」と言います。(※厳密には分けられているとははっきりは言えません。)
小まとめ

表皮の皮脂層には一過性細菌という細菌が付着し、一過性細菌叢を形成している。一過性細菌は石鹸の洗浄等で容易に落とすことができます。また、角質層には常在細菌が生息し、常在細菌叢を形式していいます。それは石鹸洗い程度では落ちないということがわかりました。
特に常在細菌叢の細菌は表皮に良い影響を与え、肌の状態を保つために大きな役割を担ってくれています。(※宿主の健康状態によっては常在細菌叢の細菌も病原体としてなりうる。)
逆に一過性細菌は皮膚自体に悪い影響を与える傾向にあります。
次は、皮脂層(一過性細菌叢)や角質層(常在細菌叢)にはどのような細菌が生息していて、どのような影響を与えているのかをそれぞれ分けて紹介します。
細菌の役割

主に角質層と皮脂層で生息する細菌が分かれていますが、まずは角質層の細菌を見ていきましょう。
角質層(常在細菌叢)を形成する細菌

表皮ブドウ球菌 ( スタフィロコッカス エピデルミディス ; Staphylococcus epidermidis )
酸素があってもなくても増殖できる細菌( 通性嫌気性グラム陽性球菌 )です。
主に皮膚(角質層)や鼻腔、毛穴に常在しています。
この細菌の特徴として
- 汗(アルカリ性)や皮脂をリパーゼで分解してグリセリン(グリセロール)や脂肪酸を作り出す
- この脂肪酸は肌を弱酸性に保つ
- グリセロールは、皮膚のバリア機能を保つ
- 抗菌ペプチドを産生し、黄色ブドウ球菌の増殖を防ぐ
などの役割を担っています。
弱アルカリ性の環境が適した黄色ブドウ球菌の増殖を防ぐと同時に定着率を下げることができます。逆に言うと肌がアルカリ性になるとこの表皮ブドウ球菌は生存できません。
コリネバクテリウム ジェイケウム ( Corynebacterium jeikeium )
酸素がないと死んでしまう好気性菌( 好気性グラム陽性桿菌。)です。
皮膚や粘膜上の常在菌。脂質好性の性質があるため、鼠径部(Vライン)、直腸周囲、腋窩(脇の下)など皮脂の多い箇所に分布しています。
環境が悪いと増殖し、脂質の分解産物が体臭の成分となります。
プロピオニバクテリウム アクネス ( Propionibacterium acnes )
酸素があると死んでしまいう酸素が嫌いな細菌( 偏性嫌気性グラム陽性桿菌 )です。皮膚の細菌叢における主要構成菌です。俗に言ういわゆるアクネ菌です。特徴としては
- 酸素を嫌い毛穴や皮脂腺に存在・皮脂をリパーゼで分解しプロピオン酸や脂肪酸を作り出す
- 表皮を弱酸性に保つ
- 弱酸性環境が病原性の強い細菌の増殖を抑える
- 一般的にニキビの原因と言われているが、増殖しなければニキビの原因菌にならない
- 皮脂の分泌量が増えて毛穴や皮脂腺が塞がれたりすると、一部の株(RT4, RT5株)が過剰に増殖し炎症を引き起こしてニキビができる。
ニキビを出現させにくくするには、そもそもの皮脂の分泌を減らすか、皮脂が分泌されたとしても肌表面に皮脂が長く留まらないように洗い流してあげることですね。
皮脂層(一過性細菌叢)を形成する細菌

ここにいる細菌は病気の原因となる細菌が含まれています。一つ一つ軽く見ていきましょう。
黄色ブドウ球菌( スタフィロコッカス アウレウス;Staphylococcus aureus )
酸素があってもなくても生きていけます。皮膚表面(皮脂層)や鼻腔、毛穴に住んでいます。
スタフィロコッカス属の中では病原性が高い菌ですが存在しているだけでは問題はありません。
ただ、増殖すると炎症を起こしてきます。この炎症を「面疔(めんちょう)」といいます。
ニキビと間違うことがありますが原因となる菌が異なりますので作用も症状も異なります。顔の中心部に多いと言われ、ニキビよりも痛みが強いとされています。
この菌はアルカリ性下でも容易に生存でき(耐塩性)、皮膚が弱アルカリ性に傾くとアルカリ性に耐性がない他の菌は増殖・生存出来ないために空いたスペースに増殖して毒素を出し炎症を起こします。
ちなみにこの細菌は、よくピクニックなどでの食中毒の原因菌になることがよくある菌ですね。よく手洗いをきちんとしようと言っているのは皮脂層に定着するため、ピクニック定番のおにぎりなどの食品に付着しやすいためなんです。
カンジダ属( Candida )
数は少ないですがヒトの皮膚、口腔、膣、腸管に常在菌として生息する真菌です。基本的に免疫がかなり低下しない限りは発症はしないですね。アルカリ性を好みます。
マラセチア属( Malassezia furfur )
数は少ないですが皮膚に常在する真菌。時に癜風(でんぷう)や脂漏性皮膚炎などの表在性感染症を起こします。また、汗ばむ季節に繰り返す発疹を引き起こします。アルカリ性を好みます。
一過性細菌叢と常在細菌叢のバランスをどのように維持するのか?
- 汗や皮脂が多く分泌される夏場
- 乾燥による天然保湿成分や皮脂が減少し肌のアルカリ化
維持の要は「皮脂が多い時はそれを除き、少ない時は蓄える!」が一番合理的。
肌のアルカリは表皮ブドウ球菌が増殖できなくなってしまい、アルカリ性を好む黄色ブドウ球菌の繁殖を許してしまいます。
皮脂の量を意識しつつ、1日1回、入浴時に洗顔を必ず行うように意識しましょう。
まとめ
皮膚において細菌は保湿において重要な役割を担ってくれていることをお伝えしました。
スキンケアに必要なグリセロールなどの物質は細菌の代謝によって全て供給されることがわかりました。
さらに細菌バランスの崩れが肌トラブルの原因となることもお伝えしました。つまり、化粧水を必要に使用することはないということです。
ただ、全てが細菌で補われている訳ではありませんので、そこは注意が必要です。
細菌の栄養物はもともとはヒトにより作られた代謝物であったり、ケラチノサイトの代謝物そのものであったり、細胞から出る天然保湿成分や脂肪酸も保湿に役立ちます。そこを見逃しては意味がありません。
ケラチノサイトをきちんと機能させるにはターンオーバーがきちんと機能していなければいけませんから、睡眠も大切です。
ヒトと細菌は共生関係です。それを忘れてはいけません。
(ただ、病的な状態で肌トラブルが起きていることもあるため、全く改善が見られない場合は皮膚科にかかることをおすすめします。)
結局は肌の基本構造や基本生理を知ることで、肌トラブルやスキンケアに対する答えは自然と出てきます。
無知は罪だと私は思います。是非、肌の構造と細菌についてよく理解して、日常のスキンケアに励んでほしいと思います。
参考文献
- 目に見えないヒト常在菌叢のネットワークをのぞく | 宇宙航空環境医学 Vol.49, No.3, 37-51, 2012
- 24593239 研究成果報告書 – KAKEN
- マイクロバイオームとニキビ | 日本香粧品学会誌 Vol. 40, No. 2, pp. 97–102 (2016)
- 皮膚由来抗菌ペプチドであるカテリシジンLL-37の皮膚バリア機能調節に対する役割
D’Argenio V, Salvatore F, The role ofthe gut microbiome in the healthyadult status. Clin Chim Acta 2015. 451 (Pt A): p. 97-102. 10.1016/j.cca.2015.01.003.9) - 最新臨床検査学講座 臨床微生物学, 松本哲也, 医歯薬出版株式会社 (2017)