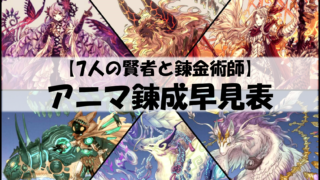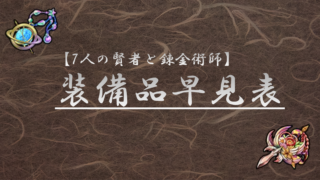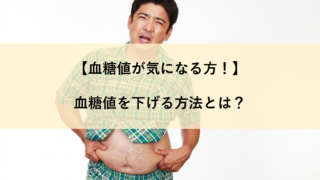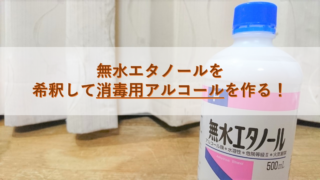今回は正しいスキンケアをする上で知っておくと必ず役に立つ情報をお伝えします。
今回の情報は、乾燥肌、混合肌、脂質肌など全ての肌質に共通する情報ですので、どなたでも読んでいただけます。
ちなみに、今回の記事は基礎的な部分なので、無駄・余計な成分だな、むしろ害だなっていう成分の話はないですが、思うことがあるため、今後はそういったところも記事で説明していきたいと思います。
本題に入る前に少し私の話を。
私、以前はスキンケアに興味がなかったです。どうでも良かったです。若かったです。
最近はカサカサと出来物が気になりすぎて、さすがに対策をしなければと思うようになりました。
カサカサは洗顔後に何もしなければ2,3分後には顔がつっぱります。というか全身乾燥肌です。
出来物は顔の中心部分に多く、特に鼻の付け根に多かいかったです。
対策をするため、顔のスキンケアについて調べ倒しました。
実践結果、カサカサは解消され、出来物は実践してから以来半年間できてません。肌も前よりも綺麗になったと言われました。
人の皮膚の体質はそれぞれ少しずつ異なり、皮膚の大まかな構造はヒトでは同じです。
今回は私が肌を改善できた理由の一つである基本的な皮膚の構造についてお伝えします。
出回ってるスキンケア情報について
ところで、インターネットに書いてある事は本当に正しいと思いますか?人によって言ってることにも違いがありますよね。
エビデンスをもとに説明されたものはほとんどありません。それっぽい物があってもさらにそのエビデンスになるものが見当たらない事もあります。
私の記事も含めてインターネットの情報は参考程度に留めておくほうが賢明です。気になったら自分で理解できるまで調べたら良いのですから。
万人に聞くスキンケア商品なんてきっとありませんよ。同じ肌質や条件の人には効くかも知れませんが。
皮膚についてそれなりの知識があれば、これは言えないしオススメ出来ないのはわかるだろうに。と思ってしまいます。
きちんとしたエビデンスを持つスキンケア商品ならば私も紹介しますよ。
不用意に言うのは閲覧者を混乱させてしまいますし、インターネットの特性上正しい知識が埋もれてしまい見つけにくくなります。自分に化粧品が合わなければ使ったお金も無駄になってしまいます。
それなら私が正確な情報を発信しようと考えたわけです。
もちろんエビデンスを意識して、できるだけ分かりやすく伝えていければと思います。専門用語を使わないと説明できない事もありますが、説明しますし、そこは頑張って理解してください。
前置きがかなり長くなりましたが、本題に入りましょう。
1万文字以上ありますし、わかりやすく説明しますが用語も出ますので理解に少し時間が必要かもしれませんので、読む場合は時間に余裕を持ってみることをお勧めします。
皮膚の基本構造
今回はスキンケアを知る上で必ず覚えておかなければいけない皮膚の構造について説明していきます。
この記事では表面の皮膚がどのようにできるかを、理解していただきたいことです。
それを理解しておくと、今後のスキンケアの仕方を見直す手がかりとなってくれます。それだけでなく肌トラブルを理解でき、対処方法まで自分で導き出すことができるようになります。
(重篤な感染症や合併で起こる皮膚症状、遺伝子疾患などには適応はできませんので、そこについては病院にかかる必要があります。)
あくまで、それ以外のことについての悩みに対応ができるようになります。
皮膚の基本構造と役割
百聞は一見に如かずです。まずは画像で構造を見てみましょう。
皮膚の全体構造を下に示しました(総合倍率 ×40倍)。
これが皮膚の構造です。顔の皮膚の構造もなんら変わりありません。

大まかな皮膚の構造
大まかには皮膚の外側から順に
1、表皮 - 外部からの刺激に対するバリア
2、真皮 - 表皮と皮下組織の結合と弾力(ハリ)
3、皮下組織 - 脂肪の層です。主に断熱
の3層からなります。
役割としては簡潔に言うと、表皮はバリア、真皮は結合、皮下組織は断熱の役割を果たします。
表皮について
表皮は皮膚の一番外側にあることはわかったでしょう。
では、具体的にはどのような構造をしているのでしょうか。
全体の構造から表皮を拡大した画像で見てみましょう。下に示します(総合倍率 ×300倍)。

表皮を上から順番に挙げていくと
皮脂層
角化(角質)層
淡明層(手掌と足底のみ)
顆粒層
有棘(ゆうきょく)層
基底層 ーここまでが表皮
乳頭(にゅうとう)層
乳頭下層
網状(もうじょう)層 ーここまでが真皮
皮下(ひか)組織
筋層
~
「太字になっている文字」はスキンケアの基礎知識としは知っておきたいところですので、是非覚えましょう。
上の画像には皮脂層はありません。理由は染色する段階で脂が取れてしまうためです。淡明層は顔にはありませんので説明は省きます。
皮膚がどのようにできるかが、今回は一番重要だと言いました。
それでは、皮膚ができる過程を簡単に説明して、下で詳しく見ていくことにしましょう。
皮膚のサイズ
まず皮膚のサイズ感を覚えてもらいましょう。
人の顔の皮膚(皮脂層~皮下組織)は性別、部位、左右さにもよりますが、0.5 ~ 2 mm 程度の厚さです。
表皮は 0.2 mm、角質層はたったの 0.02 mm 程度しかありません。
スキンケアはこの 0.02 mm という薄い部分に対して化粧品などを施しているに過ぎません。
組織学的に言うと皮膚は、角化型重層扁平上皮と言います。
「角化」とは「角化層があること」と思ってもらえれば良いです。
「扁平」とは、「平べったい」ということです。
「重層」とは、細胞がミルフィーユのように重なっているということです。
つまり、一番外側に角化層があって平べったい細胞が何重にも重なっているということ。
皮膚はどのようにできるのか
皮膚がどのようにできるのかを4段階にわけて簡潔に説明します。
①先程の画像で見た表皮の一番下の基底層にある基底細胞が分裂する
②分裂した基底細胞は分化するに従って上の層に移動しつつ扁平になる
(分化=必要な細胞に変化する。ここでは角化細胞になること)
③角質層に着いた角化細胞は外部刺激から身体を守る
④役目を終えた角化細胞は剥がれ落ちる。これがいわゆるアカ、頭皮であればフケ。
という具合の段階で皮膚が出来上がっています。
アカやフケは一般的には汚いイメージですが、実は外部からの刺激を守る重要な役割を担ってくれていた細胞なんです。
角化層へ上がるにつれて分解酵素やリパーゼ(脂肪分解酵素)により脂分も分解される。
ついでタンパク質を分解する酵素の作用によって細胞同士が離れ、最終的に角化は徐々に剥離、脱落していきます5)。
ターンオーバー日数と皮膚からの水分蒸発
基底細胞~角化した細胞が剥がれ落ちるこの一連の作業を「ターンオーバー」と言います。
ターンオーバー自体の意味は同じで信頼性はありますが、期間にはいくつかあるようですね。
多く見かけるのは28日ですが、この28日という根拠は見つかりませんので本当かは不明ですね。
ただ、表皮は場所によって厚さが異なります。例えば、足の表皮は分厚いんです。逆に拳の皮膚は薄めです。
四肢や足底は外部からの物理的刺激である擦過や圧力に耐えるため層が厚く14層程度です。
逆に顔などは比較的薄く10層以下 6) と言われていますね。
毎日アカがでるとするとターンオーバー数は1週間程度で全ての細胞が新しい細胞に入れ替わってしまいます。しかし、早すぎるので現実的には考えにくい。
言うならば 「15 ~ 30 日 くらい」というのが妥当なのではないでしょうか。冒頭で言った通りもちろん根拠はありませんので、流して頂いて構いません。
ただ、ターンオーバーについて勘違いしないでほしいのは
一度にすべての細胞が入れ替わるわけではないです。一度に入れ替わったら皮膚がない状態が出現してしまいますからね。
それにより角化細胞も、 ほぼ毎日アカとして剥離されています。
つまり、できては落ちて、できては落ちての繰り返しなわけです。外から見れば何も変わっていないように見えます(動的平衡)。
考えてほしいのは、かなり活発に皮膚は活動していることになります。
ということは水分が逃げる隙もあり水分不足に陥りやすい状態であることは想像しやすいと思いませんか?
ヒトは不感蒸泄(ふかんじょうせつ)といって、水分は常に皮膚の表皮から蒸発し、呼気(呼吸)によって逃げています。
1日に 1,000 ml 程が不感蒸泄で排出されています。
人の肌はもともと乾燥しやすい構造・性質になっているということです。
表皮の層構造について
スキンケアの知識でとても重要な表皮を、各層ごとに比較的詳しく説明していきます。
理解しやすいように基底層から説明していきます。
基底層
基底層には主に4種類の細胞があることを理解してほしいです。
- 基底細胞(ケラチノサイト)
- メラニン産生細胞(メラノサイト)
- ランゲルハンス細胞
- メルケル細胞
皮膚の一番外側には角化細胞という細胞が何重にも積み重なっているのですが、そのもとになる細胞がケラチノサイトです。
ケラチノサイトは細胞分裂・分化をして、表皮の上層に移動しつつ、 ケラチンという細胞の骨格(形を決める)を作ることで、角質層において、外部からの物理的な刺激から身を守る細胞となります(この過程を具体的に角化と言います)。
ちなみに、ケラチノサイト同士も細胞接着という機構でピタッと結合しています。このおかげで表皮より下からの水分蒸発を防いでいます。
細胞接着に必要なタンパク質もいくつもあり、代表的なものはにデスモソームというタンパク質があります。
厳密には、メラノサイトは次に説明する有棘層と基底層の間に存在していますがここで言っておきます。紫外線が当たるとしみが増えるのはこいつが活性化するためですね。
ちなみに、メラニンが沈着する深さで見た目の色がが異なります。
他には抗原提示細胞であるランゲルハンス細胞も存在します。
(抗原提示=外からのウイルスや細菌、中の壊れたタンパク質を捕まえてその破片を免疫細胞に示す細胞のこと)
他にも、メルケル細胞という細胞が存在しています。メルケル細胞は感覚神経終末に圧力に受容する細胞と考えられています。つまりは触った感覚を脳に伝える細胞ということです。
有棘層
表皮の中では一番層が厚い部分ですね。ケラチノサイトから分化した細胞は上層に行きつつケラチンをどんどん作り、角化する過程で扁平になっていきます。
有棘層の細胞は、基底細胞から角化する途中の細胞は有棘細胞と呼ばれ、その名の通り、刺のような突起がある細胞が存在しています。
その突起の先でデスモソームというタンパク質が細胞と細胞を橋渡しすることで接着しています。
また、層板顆粒という丸い顆粒が出現してきます。中身はグルコシルセラミドやスフィンゴミエリンという脂質が蓄積されています。脂質の構造と模式図を下に記してみました。

脂質というのは界面活性剤のように親水性基(水と馴染む)と疎水性基(油と馴染む)の両方を持ち合わせています。

つまり、脂質だけの環境だと親水性基は親水性基と、疎水性基は疎水性基とでまとまりやすく、親水性ー疎水性ー親水性ー疎水性…のように層を成すことができます。層板顆粒の層板というのはこの構造を取っています。
グルコシルセラミドは後述する角化細胞間脂質の構成要素となります。
難しいことは覚える必要ないです。まぁ脂質ができるんだということを覚えておけば良いです。 興味があれば深堀して覚えて下さい。
ホスファチジルコリン(レシチン)やスフィンゴミエリンはヒトなどの哺乳類の細胞膜を構成するリン脂質の一つです。
顆粒層
ケラチノサイトが角化していく段階で、顆粒層に達した細胞は顆粒細胞と呼ばれています。
顆粒細胞の特徴はケラトヒアリン顆粒という顆粒を新たに出現させているんです。
今まで読んできて、ちょっとややこしくなりましたので整理しましょう。ここまで読むと顆粒細胞には2つの顆粒があることが分かります。
- 層板顆粒
- ケラトヒアリン顆粒
の2種類あるということです。

まずはケラトヒアリン顆粒について軽く説明しましょう。
ケラトヒアリン顆粒とは膜に包まれることなく不整形の顆粒をいいます。電子顕微鏡で見るとなんとか色々ありますが置いておきます。
このケラトヒアリン顆粒、何物かというと、
プロフィラグリンというたんぱく質が豊富に蓄積されているんです。初めて聞く言葉なので、難しいですよね(笑)
このプロフィラグリン、スキンケアに関した簡単な言葉で言うと、
今後、角質層での水分として肌に潤いを与えることになる一番重要な顆粒となるんです。
このプロフィラグリンは顆粒細胞が角化する時にフィラグリンに分解されて外に出ます。
細胞外に出たフィラグリンはさらに分解され天然保湿成分であるアミノ酸などの成分になります。5,8)。これが潤いのもとになるのです。
角化が進むと、有棘層で出現した層板顆粒とフィラグリンは角化する過程でアポトーシス(=プログラムされた細胞死)により細胞外に出されます。
イメージをつかんでもらうために作図しました。

出た脂質は角化細胞と角化細胞の間に漂う(表現は適切でないかもしれません。)ことになります。この状態になった脂質を角化細胞間脂質と言います。
さらに、層板顆粒の脂質の一部は酵素によって分解されセラミドができます。
他にも顆粒細胞の細胞膜は酵素によって脂肪酸が外れて遊離脂肪酸として細胞外に分泌されます5)。 (取れた脂肪酸の状態を遊離脂肪酸と言います)

一方、アポトーシスした顆粒細胞は水分も無くなり、ケラトヒアリン顆粒が細胞外へ出る際にケラチンを凝集させ固く薄くなっていきます。これが角化です。
この角化した細胞が重なることで角質層を形成します。
つまり、角質層にある細胞は核がない細胞で死んでいる細胞なんですね。
角質層
実際の組織画像を見るとどこが角質層なのかがよくわかります。もう一度出しましょう。

※確証のある顔の皮膚の病理標本画像を見つけることが出来なかったため実際何層なのかは確認はできていません。
アポトーシスした顆粒細胞は角化した時点で角化細胞となりますね。
この時点での状況を一度整理しましょう。
今までの流れで読んできたことは角質層には
- 角化細胞
- 天然保湿成分
- 角化細胞間脂質
- セラミド
- 遊離脂肪酸
が存在していることになりますね。
特に天然保湿成分であるアミノ酸には、
- グリシン
- アラニン
- ピログルタミン酸(=ピロリドンカルボン酸)
- アミノ酸以外には乳酸(または尿素)
- 六炭糖(代表的なはグルコースなど)
などが含まれています。
これら天然保湿成分は角化細胞と角化細胞間脂質の間に存在することがわかっています7)。これゆえに、角質層が肌の潤いを保っていると言えるんです。
さらにヒトの脂質の間に保持されている水分量は10~20%7)あるそうです。
※ただ、この文献の参考文献がありませんでしたので、真意は不明です。
20~30%との記述もインターネット上には多くありますが、何の根拠もありませんね。
勘違いしてはいけないのはアミノ酸などのそれ自体が保湿成分ではないのに注意しましょう。
アミノ酸自体では意味がありません。ただの乾燥物です。
アミノ酸が天然保湿成分として機能するには「水」が必要です。(当たり前)
実はこの辺りは、スキンケアに関する記事やホームページではあまり詳しく書かれたものがない内容です。
実は、ヒトの角質層にある水分は具体的に以下のようなものに分けられるんです。
- ケラチンの極性(=水と馴染みやすい)部分に結合している水分子
- 天然保湿成分であるアミノ酸などに緩く結合している自由水
- 完全にフリーの状態で存在する水で、顆粒細胞の細胞質由来の水のこと
- 顆粒層以下からの水分の滲出(染み出る事)
- 不感蒸泄
- 汗などによる外からの水分供給
全て「水」を含んでしますね。
保湿はいかに水分が外に逃さないかにかかっています。
つまり、肌に潤いがあるヒトと乾燥肌のヒトとの違いは
- アミノ酸に緩く結合する自由水
- フリーで存在する水
が大きく影響しているということです。乾燥肌ではその両方が少ない状態になっているということです。 (他には、角化細胞の数が少なかったり、脂質が多すぎたりすることもありますが)
肌の潤いに必要な物は全て自分自身で作れているんです。じゃなければ赤ちゃんの肌はあんなキレイじゃないですよね。
そう考えると、天然保湿成分やフリーの水を補充してあげることができれば、乾燥肌に悩む必要はなくなるということは容易に思いつくでしょう。ですが、そんなに単純な話ではありません。
なぜ、水分は外に出て行ってしまうのでしょうか?
健常人でも不感蒸泄などで常に水分は外に逃げています。その量は人間では一定で差はありません。これは体内の状態を一定に保つために必要な働きなのです。
ただ、乾燥肌を考えると、不感蒸泄+水分の喪失があるということになります。
つまり、水分の喪失が過剰だと言ってもいいと考えらます。
つまり、その水分の蒸発を抑えれればいいのです。外から水分を補うのは間違いなのです。
外から水分を補給しても蒸発して意味がありません。
では、何が正解か。それは水分を蒸発させないように貼蓋をすることです。
そんなこと言うと、実は水分蒸発を防ぐ機構も皮膚は持っているのです。これが角質層にある先程からちょこちょこ出ている角化細胞間脂質なのです。
有棘層で一度使った画像を出します。

この構造を保ったまま、角化細胞と角化細胞の間に存在していると考えてくれればいいです。サンドイッチされているのです。(この構造をラメラ構造と言います。)
つまりこうです。

- 外部刺激から守るバリア機能
- 水分保持
- 物質の透過
の役割を担っています。
角化細胞間脂質の他の遊離脂肪酸も独自の構造(側方充填構造)を取り、水分蒸発を防いでいます。
天然保湿成分が親水性と親水性の間に詰まっていることで肌に潤いを与えているんです。なんとなく 角質層のイメージは出来たのではないでしょうか?
この機能で、ヒトの皮膚からの水分蒸発を防いでいるんです。
ラメラ構造が崩れればバリア機能は十分に発揮できません。もちろん水分の蒸発を止めることはできず乾燥します。ラメラ構造の崩れは乾燥肌に陥る原因の一つです。天然保湿成分も表皮の外へ蒸発していきます。
乾燥肌の人は、水分が少ないことに加えて、このラメラ構造をきちんと形成できていないということです。
皮脂層
今まで書いてきたことで脂質と天然保湿成分は細胞外にいる状態ですね。ラメラ構造を形成して水分保持を担うことも説明しました。
皮脂層では角質層を皮脂で覆うことで体内からの水分喪失を防いでいるんです。角質層の角化細胞間脂質と2段階で、水分蒸発を防ごうとしています。
また、新しいことを学んで頂きましょう。
皮脂というだけあって脂質が主役です。主役を具体的に言うと、「脂肪」です。
要は中性脂肪(トリグリセリド)の一部だったりコレステロールだったりですよ。
どのように脂肪が皮脂層を覆うかというと、
層板顆粒と細胞膜からの遊離脂肪酸がとれていきます。
皮脂層には色々な反応により12種類のセラミドに分解されて存在しているんです3)。
特に12種類のうち、特に3種類のセラミドであるw-o-アシルセラミドというセラミドが皮膚バリアに重要な役割をすることがわかっています4,5)。
要は、最近スキンケアで有名になっているセラミドのことです。
つまり、皮脂層を形成する成分としてはw-o-アシルセラミド、トリグリセリド(中性脂肪)や遊離脂肪酸、コレステロール3)、スクアレンなどが生合成され皮脂層の皮脂として存在しているのです。
色々物質の名前が出てきましたが、これ全部脂です。
重量比で見ると、
- セラミド ー 50%
- コレステロール - 25%
- 遊離脂肪酸 - 10%~20%( 炭素鎖は22、24が多く占めています。 )
この比率でなければ角化細胞間脂質を構成することができません。
硫酸コレステロールという脂質も4%含まれていますがカルシウムイオンを介して角化細胞の層構造を接着、安定化させています5)。
スキンケアではセラミドが多く入っている化粧品もありますが、セラミドだけではいけないことはこれで分かったでしょう。バランスが大事です。
さらに、中性脂肪やコレステロールは体内でも生合成されますが、その源となるのは食事です。
きちんとした食事も肌の状態を保つには必要です。ただ逆に、脂肪成分の取りすぎは悪影響を及ぼしますので、程々の摂取が一番です。
皮膚の表皮は薄いながらも色々な物が存在し働いていることがわかりました。かなりダイナミックな動きをしているんですね。
真皮
次は真皮層について書いていきますが、今回はスキンケアについてですので詳しくは書きません。必要ないと思った方はまとめまで飛んでください。
乳頭層・乳頭下層
基底細胞直下には乳頭層、毛細血管が水平に走行する乳頭下層があります。
乳頭層および乳頭下層には免疫担当細胞が存在し、知覚の受容体となる小体とその神経終末が伸びています。ここでは言う知覚は触覚、圧覚、痛覚、温覚、冷覚などの感覚のことです。
小体にも名前がありますが今回は関係ないので割愛します。
網状層
網状層は大きく
- いくつかの付属器官
- 線維
に分かれます。付属器官について簡単に説明しますね。
- 毛細血管
- 肥満細胞(アレルギーに関与)
- 毛髪
- 皮脂腺
- 汗腺
などのことです。 聞いたことはあると思うので「ふ~ん」って感じですよね。
網状層の上の部分には、肥満細胞が毛細血管の近くに集中し、アレルギー反応に応答しています。
毛根・皮脂を分泌するための腺管もあります。特に皮脂は毛根の途中に存在していてるため、毛穴に開口し、毛髪の周りから分泌されます。
汗腺も存在しますがアポクリン汗腺とエクリン汗腺の2種類存在しています。
アポクリン汗腺は脇の下に集中して存在し、顔にはないとされているためここでは触れません。
一方、エクリン汗腺は全身の皮膚に存在し、体温調節のため汗を直接皮膚表面に汗を分泌しています。もちろん顔にもあります。
付属器官はざっとこんなもんで良いでしょう。
最後に真皮で一番重要な部分である線維について少し書きます。
網状層で一番大事な役割は、外部からの物理的な刺激や、皮膚その物の強度を保つという重要な役割を果たしています。
身体がバラバラにならなかったり皮膚に可動性があるのはこれらがあるためです。
分かりやすく言うと骨格の役割もあります。ヒトで言ったら骨です。骨がなかったら人間ぐにゃぐにゃで立ってられませんよね?
組織学的に言うと支持組織と言います。(支持=支えるのです。)真皮は結合組織である膠原線維や弾性線維が豊富な部分なんです。
膠原線維? 弾性線維? って感じだと思いますので説明します。
膠原線維に含まれいるのが、みんながよく知っているコラーゲンです。
コラーゲンといっても全てのコラーゲンが線維としての役割を持つわけではありませんが、真皮に存在するのはⅠ型とⅢ型のものが多く占めています。
Ⅰ型はいわゆるコラーゲンですね。「コラーゲンたっぷり」とかよく言いますよね。
コラーゲンとだけ言うなればだいたいこのⅠ型を意味します。
Ⅲ型はコラーゲンの中でも細網線維といって小さい線維が3次元的に縦横無尽にはり巡っています。
また、基底細胞と真皮の境界にある基底膜にはⅣ型コラーゲンを含み裏打ちをしています。
次に弾性線維についてですが、肌に弾力(ハリ)を与えると言われているのが弾性線維なんです。
エラスチンと言われれば分かる方もいるのではないでしょうか。
よく学習した項目だと、体の中でエラスチンが多く存在しているのは大動脈や肺なんですね~、大動脈は血液を全身に送り届けなければならないため、強度と弾力が必要なんです。
それも2重構造(内弾性線維と外弾性線維)なんです。肺では息を吐くために弾性線維の持つ収縮力が必要になってきますし、肺の形状を保つ役割もあります。あとは子宮も弾性線維を含んでいます。
つまり、真皮に存在するエラスチンも同様の役割を担います。つまり形状記憶ですね。
少し大ざっぱな考えですが皮膚を引っ張っても元に戻るのは弾性線維であるエラスチンが伸縮性に富み、伸びても元に戻る性質を持ち合わせているためです。
またコラーゲン繊維はよく美容系で良く耳にしますので知ってる方も多いと思いますが、やっぱり重要と言うことが書かれています。
皮膚が薄くなる原因には不明な点が多いが, Shusterら2)は加齢に伴う真皮コラーゲン密度の低下を指摘しており, 更に皮膚厚とコラーゲン量の間には相関があると報告している。それによれば加齢と共に真皮がコラーゲンを失ないそのため皮膚が薄くなると考えられています1)。
ちなみに、女性では皮膚の薄さはアンドロゲンやテストステロンなどのホルモンによって左右されるようです。
真皮のその他と皮下組織
皮下組織より下の層はスキンケアにはあまり関係ないので今回は説明を省きます。
リンパ管、血管、神経叢(そう)、皮下脂肪が存在します。さらに下には筋層(内輪筋、外縦筋)からなります。
スキンケアには必要なくてもいずれにしても生命にとっては欠けてはいけないものです。
まとめ
書いてきたことをまとめておきましょう。
- スキンケアに必要な皮表皮の厚さは、0.2 mm。
- 不感蒸泄で常に皮膚からは水分が蒸発している
- 基底細胞は徐々に角化していく
- 角質層の細胞は死んだ細胞だということ
- 角質層の角化細胞は、外部刺激からのバリア機能として働く
- 役目を終えた角化細胞はアカとして剥がれ落ちてる
- 基底層には免疫免疫担当細胞であるランゲルハンス細胞やメラノサイトがある
- 有棘層では層板顆粒が、顆粒層ではケラトヒアリン顆粒が出現する
- 層板顆粒は角化細胞間脂質として皮膚から水分の蒸発を防ぐ
- ケラトヒアリン顆粒は天然保湿成分であるアミノ酸を含み、肌に潤いを与えるもととなる
- 保湿の本体は天然保湿成分に結合する水やフリーで存在する水である
- 皮脂層ではセラミド、遊離脂肪酸、コレステロールがバランスよく存在することで水分喪失を防いでいる
- 真皮では繊維が肌の形とハリを保っている
長かったでしょう。ここまで読んでいただきありがとうございました。
ここまで読んでくれた方はきっとスキンケアにおける皮膚の構造と基礎知識はバッチリです。
次回は、もう一つスキンケアで重要な知識として知っておくべき内容をお伝えしたいと思います。
それは、「皮膚の常在細菌」です。
彼ら菌も肌、特に水分喪失を防ぐために大きな貢献をしてくれています。
さらに、常在細菌を学ぶことでできもの、ニキビ、肌の炎症に適切に対処することが出きるようになることでしょう。
次回をお楽しみに。
ではでは。
参考文献
組織の画像
梶ヶ谷 博, 熊谷 佑子, 松並 平晋, ひとの組織学カラーアトラス, pp.116-117, (2017)
1)超音波断層撮影装置による顔皮膚厚の測定, 傳田光洋 高橋元次, Measurement of facial skin
thickness by ultrasound method. Mitsuhiro Denda, Motoji Takahashi, J. Soc. Cosmet. Chem. Japan. Vol. 23, No. 4 1990 319
2) The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density, S. Shuster, M. M. Black and E. Mcvitie, Br. J. Dermatol 93 639-643 (1975)
3)セラミドの代謝産物の皮膚における役割
Journal of Japanese Biochemical Society 89(2):164-175 (2017) doi:10.14952/SEIKAGAKU.2017.890164
4)皮膚バリア形成に最も重要な脂質(アシルセラミド)の産生の分子機構の全容を解明
https://www.amed.go.jp/news/release_20170302.html
5)ケラチン
http://www.derm-hokudai.jp/textbook/pdf/1-03.pdf
6)https://www.doctors-organic.com/hyouhi/index.html
7)皮膚と化学 ―内と外の境界― 化学と教育 65 巻 2 号(2017)
前田憲寿 東京工科大学応用生物学部 教授
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/65/2/65_84/_pdf
8)皮膚の組織学、松浦忠夫, 熊本賢三, 榎原智美, 明治鍼灸大学 解剖学教室
http://www.meiji-u.ac.jp/research/files/shinkyuigaku4_123.pdf
9)皮膚由来抗菌ペプチドであるカテリシジンLL-37の皮膚バリア機能調節に対する役割
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-26461703/
10)人体の水分不感性放散, 久野寧